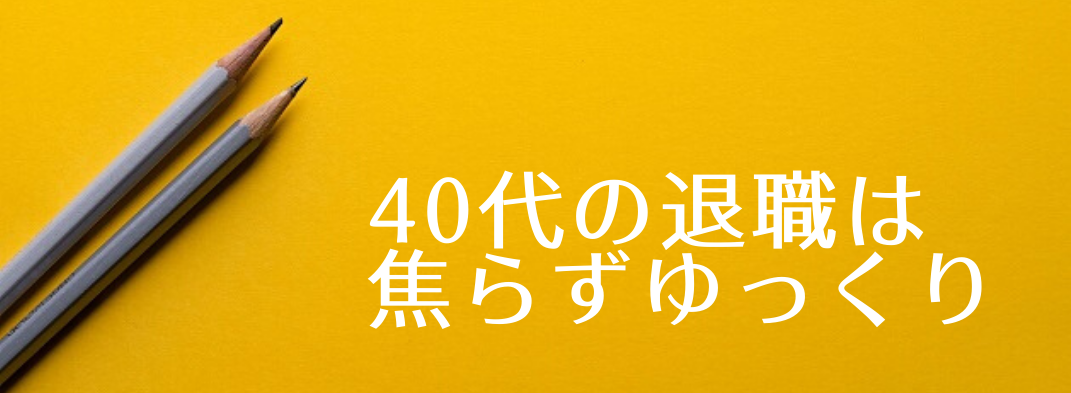40代での退職は、人生の行方をかけたひとつの大勝負です。
まずは輝かしい未来への「スタートダッシュ」を切りたいところですが、退職後に必要となる各種の公的手続きはご存じですか?
もし大切な手続きを忘れていたりすると、取り返しのつかない失敗につながりかねません。
最悪の場合、健康保険の任意継続ができなくなったり、失業給付金が受け取れなくなったりする恐れもあります。
妻子持ちの身ながら2017年、20年勤めた職場を円満退社し、現在に至ります。詳しいプロフィルは最下段にあります。
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
挽回の利かないミスを犯さないよう、退職後にやるべきことはきちんと押さえておきたいところです。
というわけで今回は、「退職後にやること」を徹底解説します。
経験者として「やっておいてよかったこと」も合わせて紹介しているほか、基本的な情報ソースとなる公式サイトのリンクも掲載し、便利な仕様にしています。
どうか最後までお付き合いください。
※下段吹き出しの登場人物
だいすけ:退職に悩む40代の会社員
みふき:筆者
Contents
【40代】退職後は自己責任に|必須の手続きは?
 40代退職希望者だいすけ
40代退職希望者だいすけ
ただ退職は初めての経験だけに何をやればいいのか…。煩雑(はんざつ)な手続きもあるようで少し心配です。
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
 40代退職希望者だいすけ
40代退職希望者だいすけ
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職直後は、慣れない「自己責任の重み」を肌で感じる分、誰しも不安になるものです。
とくに長年「バックオフィス任せ」に慣れてしまった40代退職者は、その不安もひとしおでしょう。
実際、取り返しのつかない「手続きのし忘れ」や「取りこぼし」があっても、状況次第では誰もフォローしてくれません。
そんな失敗を起こさぬためにも、「退職後にやること」は正確に押さえておきたいところです。
具体的に、退職後に必要となる公的な手続きは以下の4つになります。
- 雇用保険の手続き
- 健康保険の手続き
- 年金の手続き
- 税金の手続き
さらに、これら4つの手続きを確実に済ませるために、以下の3点が注意すべきポイントになります。
- 「会社から受け取るもの」と「個人でやること」をきちんと把握する
- 必要事項と期日をリスト化する
- 各窓口と電話で連携をとる
ここまで完璧にできればあとは簡単、ほとんど流れ作業です。
ただし手続きの方法は、転職が決まっている人とそうでない人によって異なります。
また後段で詳しくご説明しますが、転職するまで一定の期間があるか否でも、手続きの方法は変わってきます。
【40代】退職前に済ませておくべき準備
ところで、退職前にやっておくべき準備はもうお済ですか?
とくにまだ転職先が決まっていない40代の方は要注意。
40代の場合、退職前にしかできない準備を怠ると、後悔することがたくさん出てきます。
そんな失敗を犯さぬためにも、公的手続きの段取りを解説する前に、まずは退職前に押さえておきたい準備についてご紹介します。
種まきは退職前に

40代の退職者にとって、重要なポイントながらも見落とされがちなのは、退職前の「種まき」です。
退職した後は勤め先との関係が途絶え、「職場で築いた貴重な財産」を失うことになります。
とはいえ、せっかくの財産を無駄に手放すのは考え物です。
とくに約20年かけて築いてきた「人脈」はある程度、維持しておいて損はありません。
自身にとって重要度の高い人脈に対しては、退職のあいさつ時に(退職後の近況報告などを理由に)連絡する旨を伝えておくのがおすすめです。
前職で得た名刺はすべて返却する義務がありますが、「個人的な付き合」いは誰もとがめることができません。
40代で退職する場合、あらためて当人の了解を得たうえで、携帯番号を控えるなどし、つながりをキープしておくのが正解です。
転職活動
脱サラせずに、再度会社員として別の道を模索する方は、在職中の転職活動をおすすめします。
転職活動は、在職中に始めておくのが鉄則です。
退職後の転職活動は、仕事探しに専念できるメリットがあるものの、預貯金の枯渇が実質的なタイムリミットになるうえ、希望する転職先が見つかる保証もありません。
とくに40代の転職活動は、ハードルが高く、とても不利な立場に立たされるのが実態です。
同じ会社員でも「生き方自体を変える」覚悟のある方は別ですが、同等以上、あるいは現状に近い労働条件で転職先を探す場合は、無職転落へのリスクを負わず、じっくりチャンスを探るのが鉄則です。
パートナーの理解
家庭をお持ちの場合、退職後の新しい生活を安定させていくためには、夫婦の協力関係がこれまで以上に重要になります。
私の経験からしても、40代で退職に踏み切るかどうかの判断は、パートナーの理解を前提に決断するのがおすすめです。
なお、退職にまつわる妻の受け止めについて興味のある方は40代退職|妻の理解が最初のハードルに|いまの暮らしの受け止めは?という記事をご参照ください。
貯金の確保
40代で退職する場合、貯金は必須です。
転職を目指すときも、そうでない場合も、貯金は生命線になります。
上積みしておいて、決して損はありません。
私自身「もっと積み増ししておけばよかった」と後悔しています。
退職後の準備不足で苦い思いをさせられた私の経験談は「【40代退職に後悔なし!】ただし「やっておけばよかったこと」は3つある」という記事で詳しくまとめています。
また貯金を積み増す大切さについては「40代での退職に貯金は必須!【経験者が語る】もしない場合はどうすれば?」という記事で詳しく説明しています。
【40代】退職後に会社から受け取るもの

会社から「受け取るもの」と「その用途」がはっきりすると、やるべきことがある程度クリアになってきます。
退職時には、公的な証書の類をはじめ以下のものを受け取ります。
- 健康保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票1、2
- 源泉徴収票
- 厚生年金基金加入証
- 年金手帳
転職先が決まっているかどうかでも、それぞれの扱いは異なります。
証書別に詳しく解説します。
健康保険被保険者証
健康保険被保険者証は、会社が保管しているか、すでに入社時に手渡されているかのどちからかです。
まずは保管先の確認が先決となりますが、もし紛失している場合は、会社の雇用保険担当者に再交付の手続きを依頼してください。
被保険者番号さえわかれば、自分でも居住地所管の公共職業安定所(ハローワーク)で再発行できます。
なお、健康保険被保険者証は退職後、ハローワークで求職の申し込みや失業給付の手続きに必要になります。
また、再就職する場合は新しい勤め先に提出します。
| 入手先 | 自己保管もしくは会社が保管 |
| もらえる時期 | 会社保管の場合は退職日(自己保管の場合は入社時) |
| 必要になるタイミング | ハローワーク求職申込時・失業給付の手続き時 |
| タイムリミット | ハローワーク求職申込時 |
雇用保険被保険者離職票「1」「2」
雇用保険被保険者離職票は、いわゆる「離職票」のことです。
「退職日」「退職前の賃金額」「退職理由」などが記されており、「1」と「2」の2種類からなります。
退職後、ハローワークでの失業給付の手続きに必要になります。
一般的には、退職後に会社から郵送で10日以内に受け取る形になりますが、ハローワークを介しての手続きになるため、手元に届くまで2週間ほどかかるケースもあるようです。
もちろん転職が決まっている場合は不要ですが、万一に備えてもらっておいても損はありません。
| 入手先 | 会社から郵送で |
| もらえる時期 | 退職後10日以内 |
| 必要になるタイミング | 失業給付の手続き時 |
| タイムリミット | 退職後10日たつ場合は催促を |
源泉徴収票
源泉徴収票は、退職時までに受け取った年間の給料の額、社会保険料の金額、源泉所得税の金額が記されたものです。
年内に再就職する場合は、新しい会社に提出します。
年内に再就職しない場合は、所得税の確定申告に必要な書類になります。
| 入手先 | 会社 |
| もらえる時期 | 退職日 |
| 必要になるタイミング | 年末調整や確定申告時 |
| タイムリミット | 退職日が好ましい |
厚生年金基金加入員証
厚生年金基金加入証とは、厚生年金基金に加入している場合に会社から返却されます。
将来年金に加算して受け取る場合はもちろん、脱退一時金などを受け取る場合にも必要になります。
| 入手先 | 会社 |
| もらえる時期 | 退職日 |
| 必要になるタイミング | 一時金受け取り時もしくは請求年齢到達時 |
| タイムリミット | 退職日が好ましい |
年金手帳
国民年金に切り替える場合に必要になります。
再就職する場合は新しい会社に提出してください。
| 入手先 | 会社 |
| もらえる時期 | 退職日 |
| 必要になるタイミング | 国民年金切り替え時 |
| タイムリミット | 退職後14日以内 |
退職証明書
退職証明書は、退職時に自動的にもらえる証書ではありません。
退職証明書は会社発行の証書になるため、必要に応じて会社に請求する形になります。
転職先に提出を求められた場合に古巣から取り寄せるイメージです。
公的書類ではないため、すぐに発行してもらえます。
【40代】退職後の公的手続き 具体的な流れ
 40代退職希望者だいすけ
40代退職希望者だいすけ
ただ、その後の進め方について、具体的なことは何も聞いていません。被害妄想かもしれませんが、手のひらを返したように不親切な気が…。
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
 40代退職希望者だいすけ
40代退職希望者だいすけ
いずれにしても、具体的な手続きの流れを知らなければ始まりませんね。そのあたりの話題についても詳しく説明してまいります。
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
転職先が決まっていない方は、退職後、少々面倒な手続きが必要になります。
以下の枠内に大まかな流れを記していますが、これを念頭に、読み進めていただければ理解が深まります。
転職先が未定のケース(入社までに一定の空きがある場合も)
〇雇用保険の手続き
⇒離職票と雇用保険被保険者証などの必要書類を持参しハローワークへ。
〇健康保険の手続き
⇒「任意継続」「国民健康保険への切り替え」「家族の被扶養者として加入」の3つの選択肢から選ぶ。いずれが有利かは各窓口に問い合わせを。
〇年金の手続き
⇒退職日の翌日から14日以内に居住地の国民年金窓口へ。
〇税金の手続き
⇒住民税は最後の給与で天引き。退職時期によっては自分で納付(市区町村から納付書郵送)。
逆に転職先が決まっている場合、難しい作業は不要です。
下段の記事をざっと読み流す程度で理解して頂けるものと思われます。
雇用保険の手続き
すでに転職先が決まっている場合、「雇用保険被保険者証」を新しい職場に提出するだけで、雇用保険の手続きは一切不要です。
次の「健康保険の手続き」まで読み飛ばしてください。
転職先が決まっていない場合は、退職前にまず「雇用保険被保険者証」が手元にあるかどうかを確認しておかねばなりません。
手元にない場合は、会社に保管されているか、紛失したかのどちらかになります。
もし紛失したときは、会社の担当にすぐに再交付の手続きを依頼せねばなりません。
退職後は、退職後10日以内に会社から郵送される離職票「1」「2」を持参し、居住地を管轄するハローワークで「求職の申し込み」と「失業保険の給付手続き」を行います。
この際、以下のものが必要になります
- 離職票「1」「2」:離職票「1」は氏名、口座番号などを記入、「2」は賃金額と退職理由を要確認
- 顔写真付きの身分確認書類:運転免許所、マイナンバーカードなど
- 証明写真2枚:3か月以内に撮影した縦3cm×横2.5cmの正面上半身
- 印鑑:認印可(スタンプ印不可)
- 預金通帳:本人名義
- 個人番号通知書類:マイナンバーカード(通知カードでも可)、住民票
なお、雇用保険の手続きにまつわる詳しい情報はハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」に掲載されています。
失業認定日は欠席厳禁
求職の申し込みから7日間の待機期間が終了した後は、指定された日の受給説明会に出席することになります。
ちなみに手当の給付金額、給付日数などは「年齢」や「被保険者であった期間」、「自己都合か否か」などによって差があります。
受給説明会以降の流れは以下の通りです。
⇒受給説明会(求職申込日から1週間後)
⇒第1回失業認定日(求職申し込み日から約4週間後)
⇒給付制限期間(求職申し込み日から3か月間、自己都合退職者のみ)
⇒第2回失業認定日
⇒第1回基本手当振込日
⇒以降、転職先が決まるか給付日数が終わるまで繰り返し
※給付制限期間は令和2年10月以降、5年のうち2回まで2か月間に短縮。
※コロナ関連で離職した場合は「特定受給資格者」扱いの可能性も
ここでひとつ注意が必要なのは、失業認定日は絶対に欠席できない点です。
もし失業認定日をすっぽかしてしまうと、基本手当が受け取れなくなります。
また、失業認定日までの期間中、最低2回以上求職活動した実績がなければ基本手当はもらえません。
短期アルバイトなど、受給期間中に発生した収入のごまかしも厳禁で、悪質な場合は不正受給額の3倍を納付せねばなりません。
いわゆる「3倍返し」と呼ばれる制度です。
健康保険の手続き

まず健康保険証が手元にあるかをチェックしてください。
もしなければ会社の担当者に再発行の手続きを依頼します。
そのうえで、転職先が決まっている場合は、退職時に健康保険証を返却し、転職先に提出する「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります。
「健康保険資格喪失証明書」を転職先に提出すれば、健康保険証を再発行してもらえます。
とくに間を置かずに転職する方は、このまま次章「年金の手続き」まで読み飛ばしてください。
再就職先が決まっていない、あるいは入社までに一定の期間がある場合は、選択肢が以下の3つに増えます。
退職後の選択肢
- 任意継続制度の活用(最長2年)
- 国民健康保険制度への切り替え
- 家族の被扶養者として加入
健康保険に関する退職後の選択肢として、以下にさらに詳しく説明します。
任意継続制度の活用
いわゆる任意継続と呼ばれる制度で、これまで加入してきた健康保険に引き続き加入する選択肢です。
ただし退職後は、給与から天引きされていた保険料に、会社負担分を上乗せして支払う形になります。
退職日の翌日から20日以内に手続きを行わねばならず、タイムリミットの失念にとりわけ注意が必要な手続きの一つといえます。
国民健康保険よりも割安にるケースが多いものの、条件次第で逆転するため、窓口に問い合わせるのが鉄則です。
問い合わせ先は、在籍中に加入していた健康保険の係になります。
なお、任意継続にまつわる詳しい情報は、全国健康保険協会のウェブサイト「任意継続とは」の頁に掲載されています。
国民健康保険への切り替え
退職日の翌日から14日以内に、居住地の市区町村役場で手続きします。
保険料は、「昨年の所得」や「扶養に入れる家族の人数」などによって変わります。
任意継続とどちらが安いか、窓口に問い合わせたうえで選択するのが基本です。
問い合わせ先は、居住地を管轄する市区町村役場の国民健康保険係になります。
また詳しい情報については、各市区町村のウェブサイトに掲載されています。
家族の被扶養者に
3つ目の選択肢は、家族が加入する健康保険制度に被扶養者として加入する方法です。
ただし、「被保険者によって生計が維持される3親等内の親族」「被扶養者の年収が130万円以内で被保険者の年収の半分以下」などの厳しい条件が課せられています。
問い合わせ先は、扶養者が加入する保険機関になります。
年金の手続き
年金手帳も入社時に手渡しされている場合と、会社が保管しているケースに分かれます。
もし見当たらないときは、会社の社会保険担当者に再交付の手続きを要請する必要があります。
月をまたがず転職する方の場合は、手続きも簡単で、年金手帳を新しい会社に提出するだけでOKです。
「転職先が決まっていない」もしくは「決まっているが入社日が月をまたぐ」場合は、これまでの厚生年金から「国民年金」に切り替えねばなりません(60歳以上を除く、配偶者も同様)。
手続きとしては、退職日の翌日から14日以内に居住区管轄の市区町村役場、国民年金係で手続きを行う流れになります。
必要書類は以下の4つです。
当日持参するもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 退職日が証明できるもの(離職票など)
- 身分証明書
会社が厚生年金基金に加入している場合は、厚生年金基金加入員証明書も返却されます(入社時に受け取っている場合は別)。
退職後に当該の基金から書類が郵送されてくるため、記された指示に従って手続きを行います。
電話で問い合わせながら、作業を進めていくのがおすすめです。
なお、国民年金の切り替えをめぐっては、日本年金機構のウェブサイト「会社を退職したときの国民年金の手続き」により詳しい情報が掲載されています。
税金の手続き
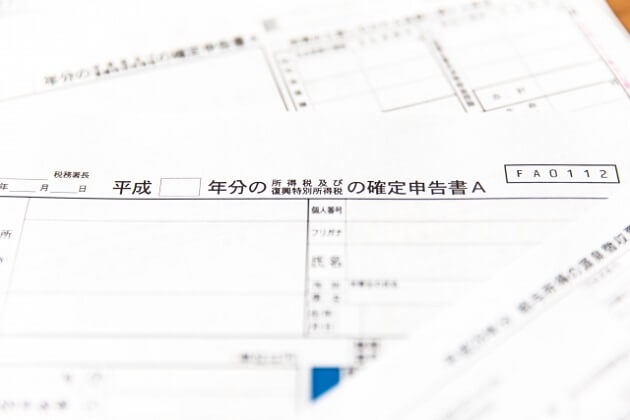
税金の手続きは「所得税」と「住民税」の2つがあります。
それぞれ、再就職のタイミングや退職月次第で手続きの方法が変わってきますので、個別に解説してまります。
なお、退職金が支給される場合は、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社の担当者に提出してください。
この申告書を提出し忘れると、退職金の確定申告を行わねばならず、とても面倒なことになります。
所得税
退職日に会社から「源泉徴収票」を受け取ります。
もし年内に再就職する場合は、次の勤め先で「年末調整」に利用します。
年内に再就職しない場合は、この源泉徴収票を使って、所得税の確定申告を行う流れになります。
税金が還付されるケースが多いため、確定申告は必ずしておきたいところです。
なお、確定申告については国税庁のウェブサイト「初めて確定申告される方へ」が便利です。
住民税
住民税は、6月を分岐点に徴収方法が異なります。
退職日が1月~5月の場合は、会社が給与から天引きしてくれるので、手続きの必要はありません。
逆に退職日が6月~12月の場合は、通常通り会社が1か月分給与から天引きし、残り5か月分は個人で納付する流れになります。
ただ、居住地の市区町村から納付書が郵送されてくるため、役場に出向く必要はありません。
会社と相談の上、一括で給与天引きしてもらうことも可能ですが、もし次の勤め先が決まっている場合は、転職先を口外せぬのが鉄則となるため、あまりおすすめはできません。
【40代】退職日の動きと会社に返すもの
 40代退職希望者だいすけ
40代退職希望者だいすけ
あとは退職日当日に返却すべきものを忘れずに返すだけです。
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
 40代退職希望者だいすけ
40代退職希望者だいすけ
 退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
退職プロみふき (40代退職経験の元記者)
会社から受け取るものを含め、公的な手続きの進め方を解説してまいりましたが、「会社に返さねばならないもの」も見落とせません。
昨今、会社の機密や個人情報の漏洩などへの配慮も重要になっています。
以下に示すのは最低限必要な返却物ですが、判断に迷う場合は上司に相談の上「とりあえず返却しておく」のが正解といえます。
- 社員証
- 社章
- 名刺(自分の名刺だけでなく、取引先分も)
- 制服・作業服
- 文房具や備品など
- 通勤定期
- 会社の資料やプログラム
- 経費の精算
【40代】退職日にやっておくべきことは?

何かとバタバタする退職日当日。
やっておくべきことを失念しないよう、あらかじめ整理・把握しておくのがおすすめです。
円満退社の場合は、総務・庶務による「交通整理」も期待できますが、そうでない場合は何が起こるか分かりません。
以下に具体例を列挙しましたので、ぜひ参考にしてください。
- 社内のあいさつまわり
- 会社からの預かりものの返却(「退職時に返すもの」の記事参照)
- 通勤定期の精算
- 立て替え中の経費の精算
- 会社から受け取るものの確認(「会社から受け取るもの」の記事参照)
- 健康保険証のコピーをとる(あると何かと便利)
- 離職票など後日受け取るものの受け渡し方法の確認
【40代】退職後にやるべきこと まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は退職後にやるべき公的手続きなどについてご紹介しました。
まとめは以下の通りです。
- 退職後に必要となる公的な手続きは4つ
- すぐに転職する時とそうでない場合で手続きは異なる
- 各公的手続きの期日は厳守を
- 認定日を失念すると失業給付がもらえなくなる
- 会社から受け取るものと返却品を理解しておく
- 築いた人脈は退職前に維持できるよう工夫を
- 退職日にやるべきことの把握を
最後までお読みいただき、ありがとうございました。